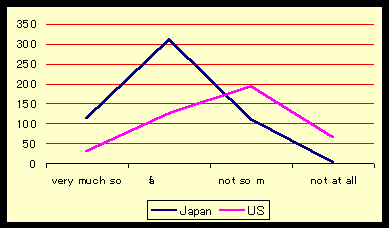② 日米の学生の日常生活比較
今回の調査に参加した学生・生徒の日常生活はどのような実態なのかを始 めに解析します。 日米双方の若者達の現実的な生活世界はどうなっているのか。 若者達はどのような意識を持って日々の生活を送っているのかをまずは見てみま しょう。
2-1:テレビ視聴時間と情報環境について(Q14,Q15) How much TV do you watch each week day ?
今回の調査では、日米間にテレビを見る時間の長さで大きな違いがありました。 米国では1日1〜2時間が主流であるのに対し、日本では3時間以上と答えた者が最 も多くいました。 この傾向は高校生では更に顕著で、3/4の日本の高校生が1日 2時間以上テレビの前に座っている一方、米国では1日当たり30分から1時間と答え た高校生が最も多くいました。
学校における拘束時間はほぼ同じだけに、子どもたちの日常生活の行動範囲の 大きな差異が想像されます。 家庭外、学校外の日本の社会教育施設がまだ不十 分であることもこの結果の一因としてあげられるでしょう。
また、取得希望学歴別に見ると、高卒希望グループに3時間以上見る傾向が強 く、大学以上の学歴希望者は視聴時間が短い傾向が見られます。 個人の勉強時 間との関連性も推測されます。
テレビを見る時間が長ければ、それだけ影響も受けることは明らかでしょう。 米国ではテレビを情報源とする者が1/3に過ぎないのですが、日本ではその数が 8割にのぼっています。
rural schoolである米国のNW高校と日本の高校ではテレビが主な情報源になっ ています。
しかし、大学ではその比率が下がり、高校でも学園町にあるI高校では、テレ ビから得る情報は皆無とする者が26%もあり、テレビからの情報に依存しないも のが8割以上もいることからみても、同じ米国の高校でも社会層が異なると、か なり違った結果が出る好例となっています。 この結果で見る限り、テレビの若 者達に与える影響度は日本において数段強いといえます。
Do you feel TV is your primary source in getting information as a whole?