4-3: 入試制度および「一流校」評価
「受験地獄」という語が存在するか否かだけでも、入試制度に対する両国の反 応の違いは容易に予想できるものです。 予想通り、日本の場合、『かなり満足 している』者は1%にも満たず、『まあまあ満足』な者も3分の1という結果が出 ています。 大学になると『かなり不満』な者が更に増え、受験経験者にとって の不満度は募るばかり、というのが日本の入試制度に対する学生の本音のようで す。
一方、米国では基本的には高校の成績を中心とする書類審査とSATの点数によっ て入否が決定するシステムが形成されていますが、この制度に対して不満な者は 2割にも満たないという結果が出ています。「中位あるいはややその下」とされる 公立M大学においても、高校生の受け止め方と全く変わらない結果です。 総じて 米国の学生の入試制度に対する肯定的態度の高さには驚かされます。
このような結果の背景には、「実力」に対する正当な評価や物差しが社会に存 在するかどうかといった、より大きな文脈における人物評価システムの存在の有 無が関係していることも予想されます。Are you satisfied with the way students are admitted to college?
「あなたは一流大学を卒業することが、将来就職に有利に働くと思いますか」 という問いに対する回答にその一端を見ることができます。 米国は、日本で考 えられている以上に「学歴社会」であり「学校歴社会」である、というのが本当 のところです。 中卒者と大卒者の初任給の差異は日本の3倍以上もあり、ブラ ンド大学の威信は日本のそれと勝るとも劣らないものがあるのです。 日本以上 に大学生や大学の数が多い米国では、日本以上に『どの大学を出たか』というこ とに重きがかかる社会意識が存在しています。
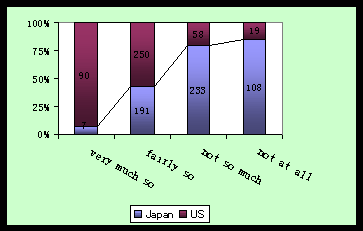
What significance do you think a diploma from a prestigious university has in getting a job?
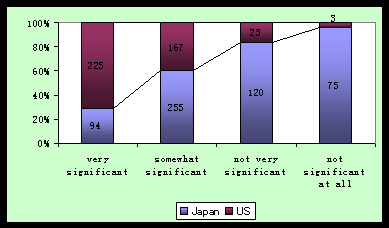
この社会意識を裏付けるように、今回の調査でも米国では高校/大学、また地 域やレベルに関係なく、「一流校」を卒業することが、将来有利に働くと共通し て認知されている度合いが顕著に高いことが、データによって証明されています。
「一流」の大学に入る者は多くの面で「一流」の実力を備えているという社会 認識がある米国に対し、学校の点数だけを「一流」と直結させる日本では、「一 流」大学に対して、特に「一流」以外の高校生は、積極的な評価を与えていない といった特異なねじれ現象が見られます。
大学進学率が比較的低い公立N高校の生徒は、上記の設問に対し、半分の者が 否定的に答えているという結果になっています。 しかし一方、受験を実際に経 験し、「一流」以外と目される大学に入った4分の3の学生が、「一流」の評価が 一面的ではあれ、「一流」の看板を認めざるをえない回答をして、高校生とは対 照的な反応を示しています。